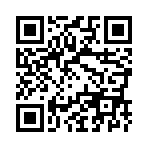2022年10月18日
初心者が考える、サバゲ―の「暖かさ」
こんにちは、サバゲ―初心者のNです。
今回は、サバゲ―を初めてまだ半年も経っていない私の所感を書き連ねるだけの記事となります。
未熟ゆえに見苦しい文章表現等があるかもしれませんが、暖かい目でご覧いただけると幸いです。
私が新歓会に初めて参加した時、私は銃が小気味よく音を立てて動作することへの興奮を覚えたと同時に、形容しがたい「暖かさ」を感じました。新入部員に優しくしようという先輩方のご厚意があったことはもちろんですが、それとは似て非なる「暖かさ」でした。
新歓会以降、定例会に何度か参加する中で、あの「暖かさ」が何に起因するものなのか、なんとなく検討がついたように思います。
1つは、共通の趣味を通じて他者との交流の輪が広がっていくことへの「暖かさ」です。
例の感染症が流行して以降、人々は自粛生活を送る過程で、他者とのつながりの重要性を再認識したように思います。
私自身、感染症対策の一環として大学でリモートやオンデマンドの授業形態が推し進められた結果、交友関係を深めづらい環境下にあったからこそ、サバゲ―を通して”同志”と語り合うことに、ある種の人間性を感じられたのかも知れません。
そしてもう1つは、そんな”同志”とより長く語らいたくなるような居心地の良さに起因する「暖かさ」です。
この記事をご覧になっている方はすでにご存じでしょうが、サバゲーをするにあたり、プレイヤーには自律の精神が求められます。これは、ヒットの自主報告と他者への配慮がサバゲ―のルールの根幹に存在するからです。裏を返せば、誰か1人が自身の感情や意向を優先した場合、その場の雰囲気、ひいては雰囲気を良くしようという皆の思いやりすらも壊しかねません。
だからこそ、私はサバゲ―プレイヤーに対し、他のスポーツや趣味をたしなむ他の誰よりも紳士で、誠実な印象を受けました。先述の居心地の良さは、彼らのそんな精神の現れだと言えるでしょう。

・愛銃SCAR-Hを構える筆者(グレー迷彩)

・休憩時の同志と筆者(グレー迷彩)
というわけで、本記事は以上となります。今後も気が向いたら記事を投稿するつもりでいますので、その際はご覧いただけると幸いです。
今回は、サバゲ―を初めてまだ半年も経っていない私の所感を書き連ねるだけの記事となります。
未熟ゆえに見苦しい文章表現等があるかもしれませんが、暖かい目でご覧いただけると幸いです。
私が新歓会に初めて参加した時、私は銃が小気味よく音を立てて動作することへの興奮を覚えたと同時に、形容しがたい「暖かさ」を感じました。新入部員に優しくしようという先輩方のご厚意があったことはもちろんですが、それとは似て非なる「暖かさ」でした。
新歓会以降、定例会に何度か参加する中で、あの「暖かさ」が何に起因するものなのか、なんとなく検討がついたように思います。
1つは、共通の趣味を通じて他者との交流の輪が広がっていくことへの「暖かさ」です。
例の感染症が流行して以降、人々は自粛生活を送る過程で、他者とのつながりの重要性を再認識したように思います。
私自身、感染症対策の一環として大学でリモートやオンデマンドの授業形態が推し進められた結果、交友関係を深めづらい環境下にあったからこそ、サバゲ―を通して”同志”と語り合うことに、ある種の人間性を感じられたのかも知れません。
そしてもう1つは、そんな”同志”とより長く語らいたくなるような居心地の良さに起因する「暖かさ」です。
この記事をご覧になっている方はすでにご存じでしょうが、サバゲーをするにあたり、プレイヤーには自律の精神が求められます。これは、ヒットの自主報告と他者への配慮がサバゲ―のルールの根幹に存在するからです。裏を返せば、誰か1人が自身の感情や意向を優先した場合、その場の雰囲気、ひいては雰囲気を良くしようという皆の思いやりすらも壊しかねません。
だからこそ、私はサバゲ―プレイヤーに対し、他のスポーツや趣味をたしなむ他の誰よりも紳士で、誠実な印象を受けました。先述の居心地の良さは、彼らのそんな精神の現れだと言えるでしょう。

・愛銃SCAR-Hを構える筆者(グレー迷彩)

・休憩時の同志と筆者(グレー迷彩)
というわけで、本記事は以上となります。今後も気が向いたら記事を投稿するつもりでいますので、その際はご覧いただけると幸いです。
Posted by 北海道大学サバイバルゲーム部(同好会) at 22:24│Comments(0)
│雑記
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。